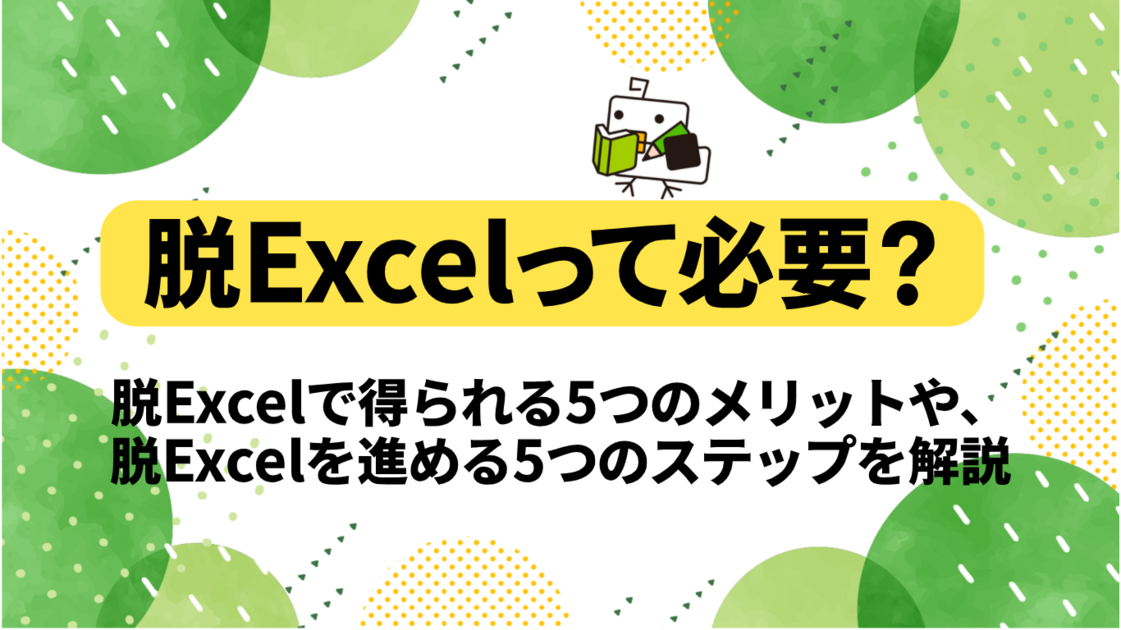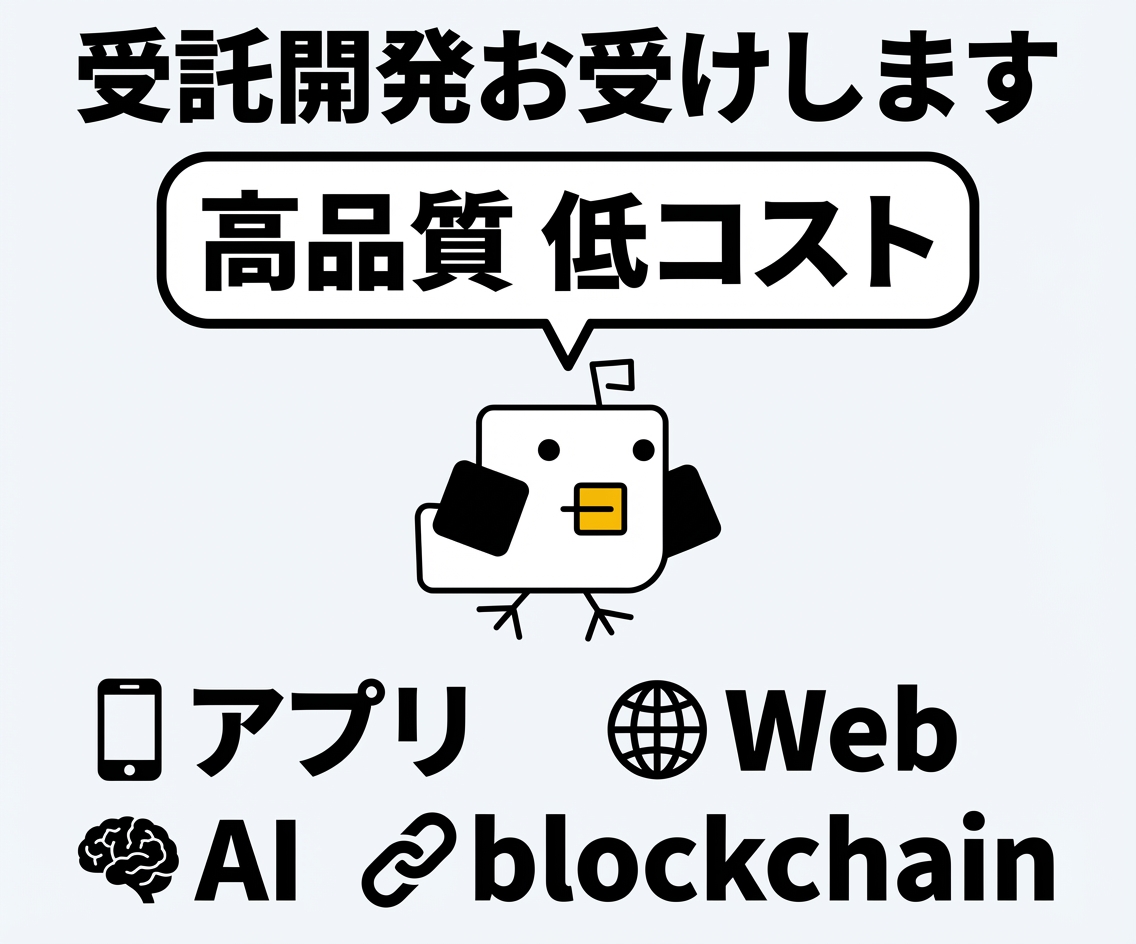【初心者必見】データ管理システムの選び方を分かりやすく解説!データ管理の現状やおすすめのシステムを紹介

目次 [非表示]
「データ管理を行いたいと思っている」
「データ管理にどのようなシステムを使えばいいのか分からない」
「初心者でも分かるよう、データ管理システムの選び方について教えて欲しい」
このような気持ちを抱いていませんか。
データを管理するシステムを導入することは、社内業務が整理・整頓されるだけでなく、作業効率が上がりチーム間の連携も取りやすくなります。
そしてゆくゆくは社内のDXを促進させることに繋がります。
しかし世の中には様々なシステムが溢れており、どのようなシステムが自社に合うのか分からないと嘆いている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、データ管理システムの選び方や、おすすめツールまで丁寧に解説していきます。
この記事を読めばどんなシステムを選べばよいのか、その判断軸が分かると思います。ぜひご一読ください!
※この記事では個人のデータ管理というよりは、企業や組織におけるデータ管理に的を絞って解説していきます。
データ管理とは
データ管理とは社内や組織にあるデータを一元化し、データを見やすく・扱いやすくすることを言います。
各個人でデータを管理することも大切ですが、組織においては「複数人で効率的にデータを管理すること」が求められます。
では複数人での管理に重要なこととはなんでしょうか。
それは「データの共有」です。
紙管理などアナログなやり方をしていると、データの共有が行いにくく互いの進捗状況が分からなくなるなど、チーム作業の効率が悪くなってしまいます。
データ管理にはクラウドサービスを利用しよう
では複数人で効率良くデータ共有が行えるシステムとは、どのようなものがあるでしょうか。
その一つがクラウドサービスです。
クラウドとは、インターネットを通してデータを管理する仕組みのことを言います。インターネット上でデータ管理を行うため、どこにいても・どんなときでも・どのデバイスからでもアクセスすることができます。
導入や運用コストも抑えることができ、保守・管理の手間もかからない製品が多いのが特徴。
自社システムを作っていくことに比べると、圧倒的に労力・コストがかからない製品、それがクラウドサービスです。
企業のデータ管理の現状
では、クラウドサービスはどのくらいの企業で使われているのでしょうか。
令和3年7月に総務省にて公表されたデータを見ていきます。

クラウドサービスの利用状況
(出典)総務省「令和3年版情報通信白書」
こちらはクラウドサービスの利用状況をまとめたグラフです。
ご覧のとおり、年々クラウドサービスの利用は拡大傾向にあることが分かり、2020年には約7割の企業において利用されていることが分かります。
そしてその効果について調べたデータを見てみると、

クラウドサービスの効果について
(出典)総務省「令和3年版情報通信白書」
クラウドサービスを利用した企業のうち、「非常に効果があった」又は「ある程度効果があった」と回答した割合は87.1%となっていることが分かり、ほとんどの人がクラウドサービスの効果を実感しているということでした。

クラウドサービスの利用内訳
(出典)総務省「令和3年版情報通信白書」
そして同調査ではクラウドサービスの利用内訳についても調べており、ファイル管理やデータ共有、社内情報の共有などを管理しているケースが多く見られました。
先述したようにデータを管理するだけでなく、社内の情報共有に力点を置いている企業が多いのです。
データ管理システムの簡単な選び方
ここまではクラウドサービスを利用するメリットや、その利用状況について見てきました。
では「クラウドサービスだったらなんでもいいのか?」と聞かれたら、答えはNOです。
ここからは製品の選び方の基準をひとつ解説していきます。
それは製品が、専門性の高いシステムなのか、汎用的なシステムなのかというポイントです。
どちらも一長一短で、良いところと良くないところがあります。
この視点で検討すると、自社に合うシステムを選ぶことができるでしょう。
- 専門性の高いシステム
- 汎用的なシステム
順番に解説していきます。
専門性の高いデータ管理システムのメリット・デメリット
何かピンポイントで管理したいことがある場合は、専門性の高いシステムを使う方が良いでしょう。
たとえば「在庫管理に特化しているシステム」や、「営業支援に特化したシステム」などです。
その分野に精通したシステムを使うことで、細かなところまで行き届いた管理を行うことができます。
しかし専門性の高いシステムは、高価なものが多いというデメリットも。
初期費用はかかるものとかからないものがありますが、かかるものだと数十万円するケースもあります。
利用料も一概には言えませんが、先述した在庫管理システムと営業支援システムについてざっと調べたところ、在庫管理システムの利用料相場は、月額3,000~70,000円で、営業支援システムは、月額3,000~20,000円であることが分かりました。
またかかる費用はこれだけではなく、機能や容量を追加したり、サポートサービスを利用するなど、円滑に使うために避けられない出費が発生する可能性もあります。
- メリット:細かなところまで行き届いた管理ができる
- デメリット:高価なものが多い
汎用的なデータ管理システムのメリット・デメリット
一方、汎用的なシステムにはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
まずメリットとしては、多様な業務で利用できるということが挙げられます。
たとえばWebデータベースだと顧客管理、タスク管理、営業管理、日報、ワークフロー、在庫管理や勤怠管理など、業種や部門をまたいで幅広く活用することができます。
またコストパフォーマンスが高い製品が多いのも特長。Webデータベースの利用料相場は月額1,500円(一人あたり)程度なので、専門的なシステムに比べると圧倒的に安価に利用することができます。
デメリットとしては、やはり専門性に欠いてしまうことがあります。しかし、機能拡張やカスタマイズなどで解消できることもあって、使い方によるところも大きいです。
メリット
- 多様な業務で利用できる、業種や部門をまたいで活用できる
- 費用が安い
デメリット
- 専門性に欠いてしまうことがある
おすすめのデータ管理システムとは?
ここまでの話をまとめると、データ管理にはクラウドサービスを使うべきであるということがひとつ。
さらに管理したいデータに基づき、専門性の高いシステムまたは汎用的なシステムのどちらかを選ぶということ。
そしてそれぞれのシステムのメリット・デメリットについて解説してきました。
ここまで読んできた方のなかには、まだどんな製品を導入するか決めかねているという方も多いのではないでしょうか。
そんな方にアドバイスしたいのは、いきなり専門性の高いシステムを導入するのはリスキーであるということです。
なかには汎用的なシステムで事足りるケースも大いにあるため、まずは汎用的なシステムを導入して様子を見ていくのが得策かと思います。
では、その他どんなところに着目して製品選びをしたら良いのでしょうか。
価格やサポート、操作性の高さなど注目する点は人それぞれかと思いますが、ひとつ特筆すべきポイントを挙げるとすれば「標準機能の充実性」です。
価格が同じくらいの製品であっても、機能が異なることはよくあります。標準機能が少ない製品だと、オプションで機能を追加しなければいけなくなることも出てくるでしょう。
するとオプション料金が上乗せされ、かかる費用が増えてしまいます。
どんな組織でもシステムに割ける予算は限られていると思います。ならば、なるべく高機能かつコストパフォーマンスが高い製品が良いと思うのではないでしょうか。
そのような観点からオススメしたい製品があるので、紹介していきます。
WebデータベースソフトのPigeonCloud(ピジョンクラウド)
PigeonCloud(ピジョンクラウド)は、株式会社ロフタルが提供するクラウド型のWebデータベースソフトです。
PigeonCloudは専門知識が一切不要なノーコードツール(※)で、汎用的なデータ管理が可能です。
データの共有・一元管理が可能で、画像添付も可能になっています。またAIを使って自動でシステム構築ができたり、RPAのように業務を自動実行できる機能も搭載されています。
そんなPigeonCloudの魅力は、「価格」・「標準機能の充実度」・「サポート力」です。
PigeonCloudは他社と比べても低価格なツールです。
またPigeonCloudは通常プランの他に「同時ログインプラン」があります。こちらは同時に接続するユーザー数で費用を計算するため、利用頻度が低い社員が多くいる場合でも費用負担が少なく、お得に使っていくことができるプランです。
また他社では別途費用がかかるような、「帳票出力」や「ルックアップ自動取得」、「自動採番機能」など高度な機能が標準装備しています。
そしてデータベースの初期構築を無料で行っているほか、導入後も無料で電話やチャット等から相談をすることができます。
PigeonCloudはコスパが高く機能も充実しているため、「なるべく予算は抑えながらも良いものを使いたい!」そんな方にぜひ使っていただきたいソフトとなっています。
(※)ノーコードとは、プログラミングを一切行わずにサービスやソフトウェアを開発することを言います。ドラッグアンドドロップで操作可能なので、専門知識やスキルがなくても短期間でシステム構築を行うことが出来ます。
- ユーザー数プラン 1,100円/一人あたり
- 同時ログインプラン(利用者数は多いけれど同時に接続する人は少ない場合、お得に利用できる)
- 脱Excel、脱Access、脱スプレッドシート等におすすめ
- スマホ、タブレットOK
- ノーコード
- さまざまな業務に使える
- AIで業務システムを自動で作成
- 低価格
- 同時ログインプランあり
- データ容量100GB
- サポートが手厚い
- 標準機能が充実
- データ分析機能
- クラウド型、オンプレミス型に対応可能
- チャットツール等との外部連携
- 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証取得
- RPAのように業務を自動実行できるコネクト機能搭載
公式サイト:PigeonCloud
競合他社との比較記事はこちらが参考になりますので、ぜひご一読ください!
おわりに
この記事ではデータ管理システムについて解説してきました。
データ管理を行うシステムは、本当にたくさんの種類があります。そのためどれが自社に合うのか選定するのは一苦労です。
人におすすめされた製品を選んだり、親しみのある企業が開発している製品を選ぶことも、もちろん出来るでしょう。
しかししっかり吟味した製品でないと必ずボロが出ます。いや、しっかり吟味した製品であっても、いざ使ってみると「こんなはずじゃなかった・・」となることさえあります。
それは仕方のないこと、で片づけてしまうと皆さんに怒られるかもしれませんが、こういうことはよくあることなのです。
クラウドサービスの良い点は、気軽に乗り換えられるというところもあります。
初期費用のかからない製品限定にはなってしまいますが、初期投資が少ない分、合わないと分かればすぐに別の製品に切り替えることが出来るのです。
DXを行っていく皆さんにお伝えしたいのは、DXはトライ&エラーの精神が大切であるということ。
新たにデータ管理システムを取り入れるということは、新しい技術を取り入れるということですので、トライ&エラーはつきものなのです。
もし合わなかったとなれば、元のやり方または別製品に変更すれば良いだけなので、まずは気負わずに試してみることをおすすめします。
さて、この記事ではおすすめの製品も紹介しました。製品に興味を持たれた方は、公式サイトから資料請求や無料トライアルを試してみてはいかがでしょうか。
関連記事
関連記事
-
データベース2026.02.12【必見】PigeonCloud(ピジョンクラウド)の評判や口コミを徹底調査!価格や活用できる業務内容まとめ
-
データベース2026.02.04【必見】kintoneの生成AI活用事例5つ!生成AI利用のメリットや注意点を解説
-
データベース2026.02.04【必見】kintoneがAIでできることとは? kintoneと連携できるAIサービスやkintone AIラボについて解説
-
データベース2026.02.03【必見】kintone AIラボとは? kintoneのAI機能の使い方や3つの注意点を解説
-
データベース2026.01.29【徹底比較】PigeonCloudとkintoneを4つの項目から比較!それぞれが向いているケースについて解説